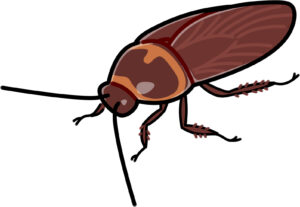ハクビシンのフンを見つけたら?ふんの特徴と対処法を徹底解説

ハクビシンは近年、都市部でも頻繁に見かけるようになった動物です。農場の果物や野菜を荒らすだけでなく、家の中に侵入してすみつくこともあります。家の付近で何かの動物のフンを見つけたら、それはハクビシンのフンかもしれません。
この記事では、ハクビシンのフンの特徴や関連する被害、そして対処法までを詳しく説明します。
ハクビシンのフンの特徴
ハクビシンのフンは、他の動物のフンとは少し違った特徴があります。形や大きさ、色や臭い、中身など、さまざまな角度からの見分け方のポイントを紹介します。
フンの形状と大きさ
ハクビシンのフンは、細長い棒状で両端が丸くなっています。大きさは長さ5〜15センチ、太さ1〜2センチほどです。小型犬のフンと似た大きさですが、形がより整っているのが特徴です。
なお、ハクビシンはすみつくと同じところに何度も排泄する習慣があるので、似た形のフンが大量にあったり、尿の強烈な匂いとともに発見されるなども特徴的と言えます。
フンの色と臭い
フンの色は黒や濃い茶色が多く、表面はつやがあります。ハクビシンは果物をよく食べるため、フンの臭いはあまり強くありません。むしろ、少し甘い香りがすることもあります。ハクビシンが消化しきれなかった果糖などの成分が残っているためです。
ただし、尿と一緒に排泄されると、アンモニア臭がすることがあります。このアンモニア臭は、尿に含まれる窒素化合物が分解されることで発生します。
フンに含まれる物
ハクビシンは雑食性で、特に果物や野菜を好んで食べます。そのため、フンの中に果物の種や野菜の繊維が混じっていることがよくあります。
混じって見られやすいものとしては、イチジクの小さな種や、トウモロコシの粒などがあります。こうした未消化物でも、ハクビシンのフンを見分けることができます。
他の動物のフンとの違い
ハクビシンのフンは、似たような場所に現れる他の動物のフンとは異なる特徴があります。例えば、タヌキのフンは、ハクビシンのフンより小さく、長さ2〜3センチほどです。色は黒く、臭いが強いのが特徴です。タヌキは昆虫類も多く食べるため、フンにはその残骸が含まれることがあります。
イタチのフンは、さらに小さく長さ6ミリ程度です。細長く曲がった形をしており、水分が多いのが特徴です。イタチは肉食性が強いため、フンには毛皮や骨の破片が含まれることがあります。
アライグマのフンは、ハクビシンのフンと似た大きさですが、形が不揃いで、昆虫の羽や骨などが混じっていることがあります。アライグマはハクビシン以上に雑食性が強く、フンの内容物は多様です。
これらの似た動物との違いを知っておくと、発見したフンがどの動物のものかを判断しやすくなります。
ハクビシンがフンをする場所
ハクビシンは特定の場所にフンをする習性があります。安全で隠れやすい場所を好むため、人間の生活圏内でも特定の場所にフンをする傾向があります。フンがよく見られる場所の特徴をここでおさえておきましょう。
屋外でよく見られる場所
ハクビシンは、屋外では主に庭の隅やベランダ、軒下、物置の周り、果樹園や畑の近くでフンをします。ハクビシンにとって安全で、かつ食料源に近い場所です。例えば、庭の隅は人目につきにくく、近くに果樹があれば食事と排泄を同じ場所で済ませることができます。
ベランダや軒下は雨風を避けられる場所で、ハクビシンにとってすみつくのに快適な環境です。これらの場所で細長い黒っぽいフンを見つけたら、ハクビシンの可能性が高いと言えます。
屋内でよく見られる場所
ハクビシンが家の中に侵入すると、主に屋根裏や天井裏、床下でフンをします。特に屋根裏や天井裏は、ハクビシンが好みやすい暗くて静かな場所です。人間の生活音から遠く、外敵の目も届きにくいため、ハクビシンにとって理想的な住処となるのです。
これらの場所でフンを見つけた場合、早急な対策が必要です。定期的にこれらの場所を点検することで、ハクビシンの侵入を早期に発見し、被害を最小限に抑えることができます。
ハクビシンのフンによる被害
ハクビシンのフンは、見た目や臭いの問題だけでなく、健康被害や家屋への損傷など、さまざまな問題を引き起こす可能性があります。具体的にどういったリスクが生じるのかを理解して、状況に合わせた対応ができるようになっておくのがおすすめです。
健康被害のリスク
ハクビシンのフンには、人間に害を及ぼす可能性のある病原菌やウイルスが含まれていることがあります。感染症のリスクを避けるために、直接触れたり、フンが乾燥して舞い上がった粉じんを吸い込んだりしないよう注意しましょう。
例えば、個体によってはサルモネラ菌やE型肝炎ウイルスなどが含まれている可能性があります。これらの病原体に感染すると、下痢や発熱、腹痛などの症状が現れることがあります。特に子どもや高齢者、免疫力の低下している人は、重症化するリスクが高いため注意が必要です。
家屋への被害
ハクビシンが屋根裏や天井裏でフンをすると、家屋に深刻な被害をもたらすことがあります。初期段階のうちに対応してしまうのがポイントです。
例えばフンや尿の水分が木材に染み込むと、腐食の原因になります。これは単なる見た目の問題だけでなく、家屋の構造的な強度を弱める可能性があります。
また、フンがかなり堆積すると重みで天井が歪んだり、最悪の場合は腐敗が原因で崩落したりする場合があり、危険です。さらに、フンの水分が電気配線に触れると、漏電や火災のリスクも高まります。
悪臭問題
ハクビシンのフン自体の臭いはそれほど強くありませんが、尿と混ざったり、長期間放置されたりすると強い悪臭を放ちます。この臭いは家全体に広がり、日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。
特に、屋根裏や壁の中にフンが溜まっている場合、悪臭は単に不快なだけでなく、頭痛やめまい、吐き気などの症状を引き起こす可能性もあるため、早急な対処が必要です。
ハクビシンのフンの処理方法
ハクビシンのフンを発見したら、適切な方法で処理することが重要です。ここでは、安全な処理方法について説明します。
処理に必要な道具
ハクビシンのフンを処理する際は、安全性を最優先に考える必要があります。まず使い捨ての手袋、マスク、ゴーグル、長袖の服、長ズボンなどの防護具が必要です。これらは、フンに直接触れたり、フンから発生する粉じんを吸い込んだりするのを防ぐために使います。
フンを掃除するための使い捨てのほうきとちりとり、フンを入れるビニール袋、そして消毒用の次亜塩素酸ナトリウム溶液なども準備します。フンに直接手を触れさせず、さらに安全かつ徹底的に消毒していくように気をつけましょう。
安全な処理手順
フンの処理は、まず、準備した防護具をしっかりと着用します。次に、フンを注意深く掃き集めます。この際、フンを乾燥させて粉じんを発生させないよう、必要に応じて水を軽く霧吹きで吹きかけると良いでしょう。
掃き集めたフンは、すぐにビニール袋に入れて密閉し、フンがあった場所を消毒液でしっかりと拭きます。使用した道具も同様にビニール袋に入れて密閉します。
最後に手をよく洗い、うがいをすれば完了です。
処理後の注意点
フンの処理をするときに身につけていた服は、可能であれば捨ててしまうのが一番です。そうでなければフンと同じく消毒作業を行いましょう。また、処理した場所の換気を十分に行い、数日間は様子を見るようにしましょう。
もし異臭が残っている場合や、新たなフンが見つかった場合は、ハクビシンがひそんでいる可能性があります。その場合は、専門家に相談することをおすすめします。
ハクビシンの侵入を防ぐ対策
ハクビシンの被害を防ぐには、侵入を予防することが最も効果的です。ここでは、ハクビシンの侵入を防ぐための対策を詳しく説明します。
侵入経路を塞ぐ
ハクビシンは小さな隙間からでも侵入できるため、家の周りをよく点検します。屋根や壁の穴や隙間、換気口や通気口、雨どいや配管の周りなど、ハクビシンが侵入しそうな場所を探し、侵入口を特定します。
特に、屋根と壁の接合部や、配管が家屋を貫通している部分は要注意です。また、木の枝が家に接している場合は、侵入路になっている可能性があるので枝を切り落とすことも効果的です。
侵入口を見つけたら金網や板で覆うなどして、ハクビシンが入れるような隙間をなくしていきます。もし侵入口がわからなくても、それらしき穴を順に塞いでいくことで対応可能です。いずれにしても必ずハクビシンが中にいないことを確認してから塞ぐようにしましょう。
餌を取り除く
ハクビシンをそもそも家に引き寄せないためには、餌となるものを家の周りに置かないことが重要です。生ゴミは必ず密閉容器に入れ、庭に放置しないようにしましょう。果樹がある場合は、実を早めに収穫し、落果した果実はすぐに拾い上げます。ペットのエサを屋外に置くことも避けましょう。
また、コンポストを使用している場合は、蓋付きのものを選び、ハクビシンが中身を食べられないようにします。
忌避剤の使用
ハクビシンは特定の臭いを嫌います。この性質を利用した忌避剤を侵入口や通り道に置くことで、ハクビシンを寄せ付けない環境を作ることができます。市販の忌避剤のほか、唐辛子やニンニク、木酢液などもハクビシンの嫌いな臭いとして知られています。
ただし、これらの効果は一時的なものであり、根本的な解決にはなりません。また、雨で流されたり、時間とともに効果が薄れたりするので、定期的な交換や補充が必要です。










-300x169.jpg)
-300x169.jpg)