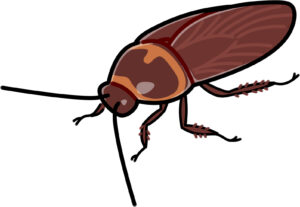アナグマとハクビシンの見分け方と対策|プロが教える特徴と駆除方法

庭や畑に見慣れない動物が現れたり、農作物に被害が出たりした経験はありませんか?その犯人、アナグマかハクビシンかもしれません。この記事では、アナグマとハクビシンの見分け方や特徴、効果的な対策方法をわかりやすく解説します。
アナグマとハクビシンの基本情報
アナグマとハクビシンは、一見似ているように見えますが、実は全く別の動物です。それぞれの特徴や生息地から、見分けられるようにポイントをおさえておきましょう。
アナグマの特徴
アナグマは、イタチ科に属する日本在来の動物です。体長は地域によって異なりますが、約50〜75cm、体重は約4〜15kgほどで、がっしりとした体つきが特徴です。顔に黒い模様があり、短い足と短い尾を持っています。夜行性で、主に地面の上や地中で生活します。
ハクビシンの特徴
ハクビシンは、ジャコウネコ科に属する外来生物です。体長は約50〜60cm、尾長は約35〜45cm、体重は約3〜5kgほどです。顔には白い線があり、長い尾が特徴的です。夜行性で、木登りが得意な動物です。
生息地と分布
アナグマは、北海道と沖縄を除き日本全国に広く分布していますが、主に山地や丘陵地に生息しています。一方、外来種としてのハクビシンは1940年代に毛皮用として日本に持ち込まれ、現在では沖縄を除き広い範囲が分布域になりました。
両種とも人里近くに出没することがあり、農作物被害や家屋侵入の原因となっています。
アナグマとハクビシンの外見の違い
アナグマとハクビシンは、似ているようですがよく見ると明確な違いがあります。顔の特徴、体型、尾の長さ、足跡など、それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
顔の特徴
アナグマの顔は、目の周りから頬にかけて黒い模様があり、鼻先は黒くてやや大きめです。一方、ハクビシンは額から鼻にかけて白く細い線が入っており、これが「白鼻芯(はくびしん)」という名前の由来になっています。
また、ハクビシンの鼻先はピンク色で小さめです。
体型と尾の違い
アナグマは、ずんぐりとした体型で足が短く、尾も短いのが特徴です。一方、ハクビシンは細長い体型で、体長とほぼ同じくらいの長い尾を持っています。この尾の長さの違いが、両者を見分けるわかりやすいポイントと言えるでしょう。
足跡の特徴
アナグマとハクビシンの足跡は、どちらも5本指ですが、細かな違いがあります。アナグマの足跡は幅広く、爪の跡がはっきりと残ります。一方、ハクビシンの足跡は比較的小さく、爪の跡はあまりはっきりしません。
さらに、ハクビシンは木登りが得意なため、木の幹や塀の上にも足跡が残ることがあります。
生態と習性の違い
アナグマとハクビシンは、食性や活動パターン、繁殖習性などにも違いがあります。姿で判別できない場合や、行動パターンを掴んで対応していきたいならこれらを覚えておくと良いでしょう。
食性の違い
アナグマは雑食で、主に昆虫類や小動物、果実、キノコなどを食べ、特にミミズを好みます。一方、ハクビシンも雑食ですが、柿やブドウなどの果実や野菜を好み、果樹園に被害を与えることが多いのが特徴です。
活動時間と行動範囲
アナグマとハクビシンは、ともに夜行性です。アナグマは、日没後から夜明け前まで活動し、日中は地中の巣穴で過ごします。ハクビシンは夕方から夜明けまで活動し、日中は木の上や建物の屋根裏などで休息します。
行動範囲は、ハクビシンが30〜70ha程度です。アナグマはそれより広く、数キロ四方に及ぶことがあります。どちらも行動範囲に複数の巣穴を持っています。
繁殖と子育ての特徴
アナグマの繁殖期は春で、いちどに1〜4頭を出産します。アナグマは、受精卵の着床遅延によって、妊娠期間は着床からおよそ2ヶ月となっています。
着床遅延とは、受精卵が着床するまでに時間がかかることをいいます。出産時期の子育ては、主にメスが担当します。
一方、ハクビシンは決まった繁殖時期はなく、年に1~2回繁殖をして1〜4頭の子を産みます。ハクビシンの妊娠期間は約2ヶ月で、アナグマより繁殖率が高いのが特徴です。
被害の特徴と見分け方
アナグマとハクビシンによる被害は、一見似ているように見えますが、よく観察すると違いがあります。それぞれの被害の特徴を知ることで、適切な対策を講じることができます。
農作物被害の違い
アナグマによる農作物被害は、主に根菜類や土の中にある作物に集中します。例えば、サツマイモやジャガイモの掘り起こし被害が典型的です。
一方、ハクビシンは果樹や野菜の被害が多く、特に柿、ブドウ、トウモロコシなどの実のなる作物を好んで食べます。また、ハクビシンは木に登れるため、高い位置にある果実にも被害が出ます。
家屋侵入と糞尿被害
両種とも家屋に侵入することがありますが、侵入経路や痕跡に違いがあります。アナグマは主に地面に近い場所から侵入し、床下や物置などを利用します。一方、ハクビシンは屋根や高い場所からも侵入し、屋根裏や天井裏を好みます。
糞の特徴も異なり、アナグマの糞は太めで形が不揃いなのに対し、ハクビシンの糞は細長く、果実の種が混じっていることが多いです。
痕跡や鳴き声の特徴
アナグマは地面を掘る習性があるため、庭や畑に穴を掘った跡が見られることがあります。また、鳴き声は低い唸り声や甲高い叫び声を出します。
ハクビシンは木に登る際に爪跡を残すことがあり、鳴き声は「キューキュー」という高い声や「グルルル」という警戒のうなり声が特徴的です。
アナグマとハクビシンの駆除方法
アナグマとハクビシンの駆除には、法律や安全面での注意点があります。追い出すだけではなく駆除も検討するのであれば、必ずおさえておきましょう。
法規制と駆除の注意点
アナグマとハクビシンは、鳥獣保護管理法の対象となっています。駆除を行う場合は、地域の自治体に相談し、必要な許可を取得する必要があります。また法律上、捕獲や駆除を行う際は、可能な限り苦痛を与えない方法を選択することが求められます。あくまで速やかに捕獲し処分することになるのです。
捕獲方法の選択
一般的な捕獲方法として、箱わなや囲いわなが使用されます。アナグマの場合は地上に設置しますが、ハクビシンの場合は地上だけでなく、木の上や屋根近くにも設置することがあります。
餌としてアナグマにはミミズや昆虫、ハクビシンには果物や甘い匂いのする食べ物を用意すると効果的です。
捕獲後の処理と対応
捕獲後の処理は、地域の規則に従って適切に行います。また、再発防止のために侵入経路を特定してから塞ぐなどの対策も重要です。
予防対策と再発防止
アナグマやハクビシンによる被害を防ぐには、予防対策が重要です。それぞれの動物の特性に合わせた対策を講じましょう。
侵入経路の遮断
アナグマ対策では、地面に近い場所の隙間をふさぎます。金網やコンクリートで穴をふさぎ、地面との隙間をなくすことで対策できます。ハクビシン対策では、屋根や高い場所からの侵入も考慮し、屋根裏や壁の隙間もしっかりと塞ぎます。
誘引要因の除去
両種とも、食べ物に引き寄せられて接近します。そのため、生ごみの管理や、落ち果の速やかな処理が有効です。特にハクビシン対策では、果樹園の管理に気を付け、熟した果実はすぐに収穫し、地面に落ちた果実も回収するようにしましょう。
忌避剤と防護柵の活用
市販の忌避剤や、天然の忌避効果のある物質(唐辛子、ニンニクなど)を利用することで、アナグマやハクビシンを寄せ付けにくくすることができます。また、電気柵や金網フェンスなどの防護柵を設置することも効果的です。
ただし、ハクビシンは木登りが得意なので、フェンスの上部も処理する必要があります。
Related Articles
関連コラム
-
ハクビシンの食べ物とは?被害対策から駆除まで徹底解説

- その他害獣
ハクビシンの生態と特徴 ハクビシンは鼻筋に白い線が特徴的な動物で、日本の多くの地域で見られます。家の...
-
屋根裏の不審な物音の正体は?動物侵入の特徴と対策、専門家による安全な駆除方法

- その他害獣
夜中や早朝、屋根裏から音が聞こえたら、何か動物がいるのかもしれません。本記事では、どんな動物が侵入し...
-
東京のハクビシン問題完全ガイド – 生態から対策まで徹底解説

- その他害獣
ハクビシンとは? 東京での生息状況 東京の街中で見かける機会が増えているハクビシン。この中型哺乳類は...
-
ハクビシンの駆除方法と費用相場は?効果的な対策と業者選びのコツ

- その他害獣
ハクビシンによる被害は、放置すればするほど深刻になりがちです。ハクビシンが家に住み着いている、あるい...









-300x169.jpg)
-300x169.jpg)