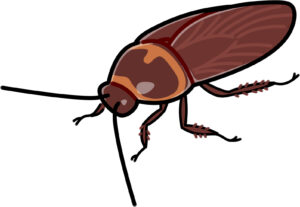日本のコウモリの種類はいくつ?家に住み着くコウモリの特徴と対処法

家の周りでコウモリを見かけたら、種類を特定して対策を始めてみましょう。
この記事では、日本に住むコウモリの種類や特徴、そして家に住み着いた時の対処法について分かりやすく説明します。早めの対策で建物や健康への被害を防ぎましょう。
日本の家屋に住みつくコウモリの種類は1種類
日本には35種類ものコウモリが住んでいますが、一般の家に住み着く可能性があるのは、ほとんどの場合「アブラコウモリ」だけです。体長4-6cmほどの小さなコウモリで、夜行性で虫を食べて生活しています。
このコウモリは1.5cmほどの小さな隙間からも入り込める上、群れで生活する習性があります。夜に活動するため人間とは生活時間が違いますが、糞や尿による被害、夜中の物音など、生活に支障をきたす可能性があるため、家の中での生息は避けたほうが良いでしょう。
なぜ家にコウモリが住みつくのか
コウモリが家に住み着く主な理由は、建物が自然のすみかと似た環境だからです。屋根裏や壁の隙間は、洞窟や木の穴のように暗くて安全で、温度も安定しています。
特に古い建物や修理が必要な家は小さな隙間や穴が多いため、コウモリが入りやすい条件が揃っています。また、街灯に集まる虫も、コウモリにとっては格好の餌場となります。
一度住みついたコウモリは、その場所を覚えて繰り返し使う習性があります。早めに発見して対策を取ることが大切です。定期的に家のチェックを行い、小さな隙間も見つけ次第塞ぐことで、コウモリの侵入を防ぐことができます。
家にコウモリが来た時に知っておきたいこと
コウモリが家に住み着いた場合、まず落ち着いて状況を確認しましょう。コウモリは人を直接襲うことはありませんが、糞や尿による衛生問題、建物の傷み、夜中の物音など、様々な被害をもたらす可能性があります。1秒も早く対応が必要というほどではありませんが、放置していいほど安全でもありません。
対処方法としては、まず侵入経路を見つけ、可能な場合は穴の大きさ1cm以下の網や金網で塞ぎます。ただし、コウモリは法律で保護されているため、むやみに捕まえたり傷つけたりすることはできません。また、病気を持っている可能性もあるため、直接触れるのは避けましょう。
自分での対処が難しい場合や、たくさんのコウモリが住みついている場合は、専門家に相談することをおすすめします。
基本家に住み着くのはアブラコウモリ一択!その特徴とは
日本の家に住み着くコウモリのほとんどはアブラコウモリです。体長4-6cm、体重5-10gと、とても小さな体を持っています。灰色がかった茶色の毛で覆われており、夕方から夜にかけて活動します。
高音の超音波を出しながら飛び、その反響で周りの様子を把握します。1晩で数百匹もの虫を食べる能力があり、わずか1.5cmほどの隙間からも侵入できます。また群れで生活する習性があり、一度住み着くと数が増えていく傾向にあります。
家の中では主に屋根裏や壁の隙間、軒下などを好んで使い、年間を通じて同じ場所に住み続けます。コウモリがいることに気付くのは、夕方や夜明けの飛ぶ姿、チッチッという鳴き声、黒い糞などからです。
アブラコウモリが起こす被害
アブラコウモリが家に住み着くと、いくつかの深刻な問題が起きる可能性があります。最も多いのは糞や尿による被害です。コウモリは1日に何度も排せつを行い、その糞や尿には強い臭いがあります。これが建材を傷めたり、木材を腐らせたり、壁紙や天井を変色させたりする原因となります。
また、夜中の物音も問題です。コウモリは夜行性のため、人間が寝ている時間に活発に動き回ります。壁の中や天井裏での羽ばたき音や引っかき音が、睡眠の妨げになることがあります。
建物への物理的な被害としては、出入りを繰り返すことで隙間が広がったり、断熱材や電気配線を傷つけたりすることもあります。
【実践編】安全なコウモリ対策の方法
コウモリ対策で最も大切なのは、まず侵入経路を見つけることです。アブラコウモリは体が小さく、1.5cmほどの隙間があれば入れてしまいます。屋根裏や外壁、換気口など、建物の隙間をよく調べましょう。
コウモリ対策をステップごとに解説していきます。
侵入経路の特定と封鎖方法
コウモリの侵入経路を見つけるには、まず建物の外をくまなく調べます。特に注意が必要なのは屋根裏に続く場所です。軒下や壊れた瓦の隙間、換気口、雨どいの周りを重点的にチェックしましょう。
侵入口が見つかったら、1cm以下の目の細かい網や金網で塞ぎます。ただし、すでにコウモリが住んでいる場合は、中にいるコウモリが出られなくなる危険があるため、まず追い出してから塞ぐ必要があります。
侵入経路が見つからない場合は、夕方から夜にかけて建物の周りを観察し、コウモリの出入りする場所を確認するのが効果的です。また、コウモリの糞が落ちている場所の真上を見上げると、侵入口が見つかることもあります。
追い出し方のポイント
コウモリを安全に追い出すには、夜の活動時間に外に出てもらい、その間に侵入口を塞ぐのが基本です。コウモリは夕方になると餌を求めて外に出ていくため、この習性を利用します。
まず昼間のうちに、コウモリがどこにいるのか、どこから出入りしているのかを確認します。次に、日が沈む前後の時間帯に、LEDライトや懐中電灯で明るく照らしたり、ラジオをつけるなどして、自然に外へ出ていくよう促します。
ただし、強い刺激を与えすぎるとパニックになって思わぬ行動を取る可能性があるため、徐々に行うことが大切です。
また、子育ての時期(主に6~8月)は特に注意が必要です。親コウモリだけを追い出してしまうと、子供のコウモリが取り残されてひっそりと死んでしまう恐れがあります。
再び住みつかせない予防策
コウモリを追い出しても、きちんと予防策を取らないと再び住みつく可能性が高くなります。効果的な予防策として、まず年2回(春と秋)の建物点検があります。小さな隙間や破損箇所を見つけたら、すぐに修理します。
コウモリは高い音で周りの様子を確認するため、音を反射する素材を使ったり、コウモリの嫌がる光や音を利用したりするのも効果的です。CDやアルミホイルを吊るしたり、LEDライトを設置したりする方法もあります。
さらに、コウモリの餌となる虫を寄せ付けないことも大切です。外灯は虫の集まりにくいLEDに替えたり、網戸や防虫スクリーンをこまめに手入れしたりするのがおすすめです。
【注意点】コウモリ対策でやってはいけないこと
コウモリは鳥獣管理保護法で保護されており、以下の行為は違法となります。
まず、許可なく捕まえたり傷つけたりすることは禁止です。罠を仕掛けることや、直接手で捕まえることも含まれます。また、コウモリの巣を許可なく壊したり移動させたりすることも違法です。特に子育ての時期は、親と子供の両方が保護の対象となるため、より慎重な対応が求められます。
これらの違法行為を行うと、罰金や懲役などの刑事罰を受ける可能性があります。不安な要素がある場合は、自治体や専門業者に相談し、適切な対処方法を確認しましょう。
専門業者に相談すべき状況とは
一般家庭でできるコウモリ対策には限界があります。次のような状況では、早めに専門業者に相談することをおすすめします。
- コウモリの数が多く、自力での追い出しが難しい場合
- 建物の構造上、侵入経路の特定や封鎖が難しい場合
- 子育て中のコウモリが見つかった場合
よくある質問
Q. コウモリは何種類くらいいるの?
世界には約980種類のコウモリが生息しており、これは全ての哺乳類の約4分の1を占める数です。コウモリは大きく2つのグループに分かれます。1つは主に熱帯や亜熱帯に住み、果物や花の蜜を食べる大型のコウモリ。もう1つは世界中に広く分布し、主に虫を食べる小型のコウモリです。
日本には35種類のコウモリが生息しており、そのうち33種は虫を食べる小型のコウモリです。しかし、多くの種が絶滅の危機にあります。
Q. 日本でよく見かけるコウモリの種類は?
日本で最も一般的に見かけるのは「アブラコウモリ」です。家に住みつくことから「イエコウモリ」とも呼ばれています。夕方から夜にかけて、街灯の周りや公園、川の近くでよく見かけます。1晩に数百匹もの蚊や蛾を食べる、人間にとって役立つ存在とも言えます。
次によく見かけるのは「キクガシラコウモリ」で、鼻の形が菊の花のように見えることからこの名前が付いています。洞窟や古いトンネルなどに群れで住んでいます。沖縄などの南の島では「オリイオオコウモリ」という大きなコウモリも見られます。これは果物を食べるコウモリで、翼を広げると1メートル近くになります。
Related Articles
関連コラム
-
エアコンのコウモリ対策完全ガイド|自分でできる安全な追い出し方から予防策まで

- コウモリ
コウモリがエアコンに住み着くことがあります。なぜわざわざエアコンの中に入り込んでしまうのでしょうか?...
-
コウモリの寿命と生態は?3~5年の寿命で繁殖力が強い理由と対策方法

- コウモリ
コウモリの寿命は種類によって大きく異なります。家屋に住み着くアブラコウモリは3~5年程度ですが、洞窟...
-
コウモリのふん、掃除の仕方は?具体的なやり方と危険性をチェック

- コウモリ
コウモリのふんを見つけたら、すぐに対処することが大切です。ふんには病気の原因となる菌が含まれているた...
-
コウモリ駆除にハッカ油は効果的?正しい使い方と注意点

- コウモリ
家の近くでコウモリを見かけて困っていませんか?コウモリは病気や寄生虫を運ぶ可能性があるので、早めの対...









-300x169.jpg)
-300x169.jpg)