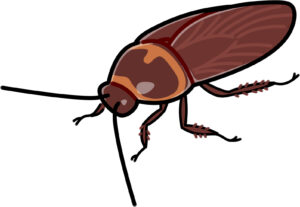コウモリの嫌いな音を使った追い払い方法とは?超音波で安全に対策可能!

コウモリは超音波を使って周りの様子を確認する動物です。音を使った対策が効果的だと思われがちですが、実は効果は限られています。
この記事では、コウモリが嫌う音を使った対策方法と、その正しい使い方を紹介します。
コウモリが嫌がる音の種類と効果
コウモリが嫌がる音は大きく分けて2種類あります。まず「超音波」です。コウモリは自分で超音波を出して、その跳ね返りから周りの様子を確認しています。そこに人工的な超音波を当てると、コウモリは混乱して方向感覚を失います。
もう1つは「ラジオの電波音」です。ラジオから出る高い電波音が、コウモリの音波探知の邪魔をします。音量は関係なく、電源を入れて電波を受信するだけで効果があります。
それぞれの特徴について詳しくみていきましょう。
人間には聞こえずコウモリに効果がある超音波とは
人間が聞ける音の範囲は20Hz~20kHzまでです。一方、コウモリは1kHz~120kHzまでの音が聞こえます。コウモリは人には聞こえない超音波を発し、物に当たって跳ね返ってくることで物までの距離や大きさを把握しています。
コウモリに効く超音波の周波数は、コウモリの種類によって異なります。家によく住みつくアブラコウモリの場合、40~60kHzの超音波が最も効果的です。これは、アブラコウモリ自身が出している超音波の周波数と同じだからです。
注意点として、超音波でのコウモリ対策は、コウモリを混乱させる効果がありますが、若い人やペットへの影響も考える必要があります。特に20歳前後までの若い人は20kHz以上の音が聞こえることがあり、不快感に繋がります。また、犬や猫も聞こえる音の範囲は人よりも広いため、影響が出る場合があります。
さらに、コウモリは音に慣れやすい性質があります。同じ超音波を続けて使うと、次第に効果が弱くなっていきます。超音波による対策は一時的な解決策と考えるのが良いでしょう。
ラジオはつけておくだけで対策可能
ラジオの受信音にもコウモリを追い払う効果があります。ラジオが電波を受信する時に出る高い音が、コウモリの感覚を混乱させるのです。
コウモリがよく来る場所の近くに置き、夕方から夜の間だけ使うようにしましょう。また、雨や風から守れる場所を選び、電波の受信状態が良い場所に設置することが大切です。
ただし、ラジオだけでは完璧な対策とはいえません。電波の届く範囲には限りがあり、広い場所では十分な効果が得られないことがあります。また、近所迷惑にならないよう、音量は控えめにしましょう。実は効果があるのはラジオの受信音なので、音量を上げる必要はありません。
コウモリの嫌いな音による対策のやり方とポイント
音を使ってコウモリを追い払う場合、正しい方法で行うことが大切です。まず、コウモリがどこから入ってきて、どこにいるのかをしっかり確認します。次に、超音波発生器やラジオを適切な場所に設置します。使用時間は、コウモリが活動する夕方から夜にかけてが特におすすめです。
以下、詳しく対策方法について解説していきます。
スマートフォンアプリで手軽に
スマートフォンのアプリを使えば、手軽に超音波対策を試すことができます。アプリストアで「超音波」「害獣駆除」などと検索すれば、コウモリ対策用のアプリが見つかります。
ただし、アプリには限界があります。スマートフォンのスピーカーでは、十分な強さの超音波を出せないことがあります。また、バッテリーの消耗も激しく、長時間使うなら充電器が必要です。スマートフォンの画面を消すと音が止まってしまうものもあります。そもそもそのアプリの仕様に根拠のない可能性もあります。
アプリによる対策は、コウモリ対策の効果を試してみたい時や、一時的な対策として使う分にはいいでしょう。しかし本格的な対策としては足りません。
市販の超音波発生器を常設する
本格的な対策には、市販の超音波発生器がおすすめです。ホームセンターやネットで購入でき、値段は2,000円から10,000円くらいです。選ぶ時は、コウモリに効果的な周波数(40~60kHz)に対応しているか確認しましょう。また、十分な音の強さが出せるか、屋外で使えるよう防水機能があるかもチェックします。
設置場所に合わせて、コンセント式や電池式、ソーラー式など電源タイプを選べます。人が来たときや暗くなった時に自動で作動する機能がついた機種もあります。
専用機器だと安定した超音波を出せる上、屋外でも使えて広い範囲をカバーできます。ただし、場所や環境によって効果は変わります。また、広い場所では複数台必要になるかもしれません。
効果を高める設置のコツ
超音波発生器やラジオは、コウモリがよく来る場所の近くに設置しましょう。できるだけ開放的な場所を選び、超音波が遮られないようにします。さらに雨や直射日光が当たらない場所で、電源が確保しやすく、メンテナンスもしやすい場所がベストです。
使用時間は、コウモリが活動する夕方から夜にかけてです。効果が感じられない時は、設置場所を変えてみるのもいいでしょう。
コウモリを追い出す際に気をつけるべきこと
コウモリは法律で保護されている動物です。むやみに捕まえたり傷つけたりすると、懲役や罰金の対象になる可能性があります。追い出しのタイミングも大切です。
ここでは、実際に追い出し作業をする際に知っておきたいポイントを解説します。
コウモリが出て行きやすいタイミングに行う
コウモリは12月から2月頃までの冬季は冬眠するため、この時期の追い出しは効果が低く、コウモリを死なせてしまいかえって困難な状況になるおそれがあります。例えば簡単に人が行けないような場所でコウモリが死んでしまうと取り出すのが非常に大変です。
また、6月から8月は子育ての時期のため、親コウモリと一緒に赤ちゃんコウモリも住んでいる可能性が高く、この時期の追い出しも避けるべきです。最適な追い出し時期は、活動が活発になる春(3月~5月)か秋(9月~11月)です。
コウモリは日中はほとんど活動しないため、夕方から夜にかけて追い出し作業を行うのが効果的です。コウモリは日没後に餌を探しに外出する習性があるため、この時間帯に追い出しを行うことで、自然な形で外に出て行きやすくなります。
必ず追い出し切ってから侵入口を封鎖する
コウモリの追い出しを行う際は、すべてのコウモリが外に出たことを確認してから、侵入口を封鎖することが極めて重要です。
もし一匹でも内部に残っている状態で侵入口を封鎖してしまうと、コウモリは出られなくなって閉鎖環境内で死んでしまい、悪臭や衛生面での問題が発生する可能性があります。
追い出しが完了したかどうかの確認として、以下の対応は欠かせません。
- 夜間の活動音や羽ばたき音を注意深く観察
- 糞の新しい痕跡がないかを確認
これらの確認を数日間継続して行い、活動の形跡が完全になくなってから侵入口の封鎖を実施します。また、一度に全ての侵入口を封鎖するのではなく、主要な出入り口を一つだけ残して他をすべて封鎖し、最後にその出入り口を封鎖するという方法も効果的です。
追い出しの効果が一時的な場合も
コウモリの嫌いな音で追い出しに成功しても、その効果はずっと続くわけではありません。音や光、忌避剤などによる対策は、時間の経過とともにコウモリが慣れてしまい、効果が薄れていく可能性があります。
また、一度追い出しに成功しても、完全に侵入経路を封鎖していない場合は、別のコウモリが新たに侵入してくる可能性もあります。
コウモリは強い帰巣本能を持っているため、一度住み着いた場所に執着する傾向があります。そのため、追い出し後の管理も重要で、定期的な点検や必要に応じた追加対策が求められます。
継続的な監視を行い、新たな侵入の兆候が見られた場合は、すぐに対応を取ることが大切です。また、プロの害獣駆除業者に相談することで、より確実な対策を講じることができます。
よくある質問
Q. コウモリが家に寄ってこないようにするにはどうしたら?
コウモリを寄せ付けないためには、超音波やラジオなどの嫌いな音だけではなく、複数の対策を組み合わせるのが効果的です。
まず大切なのは、コウモリの餌になる虫を減らすことです。LEDライトに変えたり、虫の好む光を避けたりすることで、虫が集まりにくくなります。
次に、建物の隙間や穴をしっかり塞ぎます。コウモリは2~3cmの隙間があれば入れてしまうので、定期的なチェックと修理が必要です。
Q. コウモリが家に来やすい時間帯はいつですか?
コウモリは夜行性の動物で、日が沈んでから夜明けまでの間に活動します。特に日が沈んでから30分~1時間の間が一番活発です。この時間帯は餌を探して飛び回るため、家に入ってくる可能性も高くなります。
また、朝方の日の出前にも活動が活発になり、寝床に戻る時に家に入ってくることがあります。季節によっても活動時間は変わり、夏は日が長いため活動開始が遅く、冬は日が短いため早くなります。この活動パターンを知っておくと、対策を立てやすくなります。
Related Articles
関連コラム
-
エアコンのコウモリ対策完全ガイド|自分でできる安全な追い出し方から予防策まで

- コウモリ
コウモリがエアコンに住み着くことがあります。なぜわざわざエアコンの中に入り込んでしまうのでしょうか?...
-
コウモリの寿命と生態は?3~5年の寿命で繁殖力が強い理由と対策方法

- コウモリ
コウモリの寿命は種類によって大きく異なります。家屋に住み着くアブラコウモリは3~5年程度ですが、洞窟...
-
コウモリのふん、掃除の仕方は?具体的なやり方と危険性をチェック

- コウモリ
コウモリのふんを見つけたら、すぐに対処することが大切です。ふんには病気の原因となる菌が含まれているた...
-
コウモリ駆除にハッカ油は効果的?正しい使い方と注意点

- コウモリ
家の近くでコウモリを見かけて困っていませんか?コウモリは病気や寄生虫を運ぶ可能性があるので、早めの対...









-300x169.jpg)
-300x169.jpg)