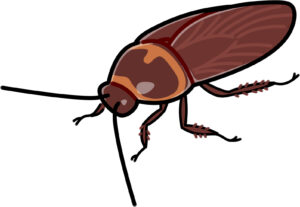イタチとハクビシンの見分け方と被害の特徴比較!対策と予防の方法も紹介

家の周りや天井裏で不審な物音や足音がする、農作物が荒らされている…そんな経験はありませんか?犯人はイタチやハクビシンかもしれません。この記事では、イタチとハクビシンの見分け方や特徴、効果的な対策方法をわかりやすく解説します。
イタチとハクビシンの基本情報

イタチとハクビシンは、体の大きさからも一見似ているように見えますが、実は全く別の動物です。それぞれの特徴や生態での見分け方を紹介します。
イタチの特徴と生態
イタチは、イタチ科に属する小型の哺乳類です。体長は20〜40cm程度で、細長い体型が特徴です。夜行性で、主に小動物や魚、昆虫などを食べる肉食に近い雑食の動物です。
イタチは泳ぎが得意で、水辺でも活動します。性格は攻撃的で、自分よりも大きな動物に対しても果敢に立ち向かうことがあります。
ハクビシンの特徴と生態
ハクビシンは、ジャコウネコ科に属する中型の哺乳類です。体長は50~70cm程度で、細長い体系ですが、イタチよりもかなり大きさがあります。体長とほぼ同じくらいの尾を持つのも特徴的です。
夜行性で、果実や野菜、昆虫などを食べる雑食の動物です。ハクビシンは木登りが得意で、高い場所にある果実なども食べます。性格は比較的臆病ですが、脅かされると攻撃的になることもあります。
生息地と分布
イタチは日本全国に広く分布しており、主に平地や丘陵地、水辺などに生息しています。一方、ハクビシンは1940年代に日本に持ち込まれた外来種で、全国各地で見られるようになりました。
両種とも人里近くに出没することがあり、農作物被害や家屋被害の原因となっています。
イタチとハクビシンの見分け方
イタチとハクビシンは、よく見ると明確な違いがあります。外見だけでなく、足跡やフン、鳴き声、行動パターンなどにも特徴があります。これらの違いを知ることで、どちらの動物が家の周りにいるのか判断しやすくなります。
外見の違い
イタチとハクビシンは、毛の色と体型が大きく違います。
イタチは細長い体型で、全身が茶色や黄褐色の毛で覆われています。顔は小さく、目が黒く丸いのが特徴です。
一方、ハクビシンは体が大きく、灰褐色の毛で覆われています。顔は少し長めで、額から鼻にかけて白い線が入っているのが特徴的です。この白い線が「白鼻芯(はくびしん)」という名前の由来になっています。
足跡の特徴
イタチの足跡は小さく、前後の足を合わせても3cm程度です。5本の指がはっきりと残り、爪の跡も見えることがあります。
ハクビシンの足跡はイタチよりも大きく、前足で4~5cm、後ろ足で7~9cm程度です。イタチと同じく5本指ですが、足の裏全体が地面に付くため、より大きな跡が残ります。
フンの特徴
イタチのフンは細長く、長さは1cm以下で直径は5mm程度です。色は黒っぽく、強い臭いがします。中に小動物の毛や骨の破片が混じっていることがあります。
ハクビシンのフンは太めの棒状で、長さは5~15cm程度です。色は黒っぽいですが、果実の種が混じっていることが多く、臭いはイタチほど強くありません。
鳴き声の違い
イタチの鳴き声は高く甲高い「キーキー」という声や、「クックッ」という短い声が特徴です。威嚇するときは「ギャッギャッ」と大きな声で鳴きます。
ハクビシンの鳴き声は「キューキュー」や「キーキー」という高い声で、イタチよりも少し長く続きます。
行動パターンの違い
イタチは素早く動き回り、小さな隙間もすり抜けることができます。水辺での活動も多く、泳ぐ姿を見かけることもあります。
ハクビシンは木登りが得意で、高い場所を移動できます。電線を歩いたり、垂直な壁を登ることまでできます。
イタチとハクビシンによる被害
イタチとハクビシンが家の周りに住み着くと、さまざまな被害が発生します。これらの被害を正しく理解することで、適切な対策を講じることができます。
家屋への被害
イタチやハクビシンが屋根裏や壁の中に侵入すると、断熱材を巣材として使用したり、配線をかじったりすることがあります。
また、フンや尿による汚染や悪臭の問題も深刻です。特にイタチは、フン以外に食べ物を巣に持ち帰る習性があるので、食べ残しが腐り悪臭の原因となります。
イタチやハクビシンが棲みつき長期間放置すれば、天井や壁に染みができたり、木材が腐ったりする可能性があります。
衛生・健康被害
イタチやハクビシンは、さまざまな病原体やダニ、ノミを媒介する可能性があります。例えば病原体は、サルモネラ菌やレプトスピラ菌などが存在し、感染すると腹痛、下痢、発熱などの症状が現れ、免疫力が低い人や高齢者では重篤化する場合もあり注意が必要です。
また、犬や猫などのペットがいる家庭では、ほかの動物からノミが移ることでペットに感染する可能性があります。ノミは、細菌性の感染症(ペストや猫ひっかき病の原因菌であるバルトネラ症など)を媒介することがあるので危険です。
人にとっても、イタチやハクビシンなどの動物の排泄物や毛はアレルギー反応を引き起こす原因となり、特に気管支系に影響を与える可能性があります。
農作物被害
イタチやハクビシンは、果実や野菜を食べて深刻な農作物への被害を引き起こすことがあります。特に、柿やブドウなどの果樹園や、家庭菜園での被害が多く報告されています。
農場に限らず、家庭菜園でも被害を受ける可能性があります。
ペットへの危険性
イタチやハクビシンは、小型のペットを襲う可能性があります。特に、ウサギ、ハムスター、鳥類など屋外で飼育している小動物は危険です。また、大型のペットでも、イタチやハクビシンと遭遇すると怪我をする可能性があります。
イタチとハクビシンの駆除方法
イタチやハクビシンを駆除するには、いくつかの方法があります。ただし、法律や安全面での注意点もあるため、適切な方法で対処することが重要です。
自力での駆除方法
自力で駆除を行う場合、まずは安全性の確保と対象の確認が重要です。直接触ったり、不意に遭遇したりすると怪我や病気への感染の恐れがあります。距離を取ること、怪我をしないように装備をするようにしましょう。
安全を確保できたら、次に侵入経路を特定します。屋根や壁の隙間、換気口などをチェックし、入り込みそうな状態になっているか見てみましょう。
周辺にふんや痕跡が残っていたら、そこが侵入口になっている可能性があります。侵入口を見つけ出し、塞ぐことが重要です。金網や板などでしっかり塞ぎます。また、餌となる食物を片付け、ゴミ箱にはしっかりとフタをすることも効果的です。
忌避剤の使用法
イタチやハクビシンが嫌う匂いを利用した忌避剤を使用することで、侵入を防ぐことができます。市販の忌避剤のほか、唐辛子やニンニク、木酢液なども効果があるとされています。設置場所は、痕跡のあった場所や通り道に設置しますが、定期的な交換が必要です。
捕獲器の設置方法
捕獲器を使用する場合は、地域の自治体に許可を得る必要があります。捕獲器は、イタチやハクビシンの通り道に設置し、好む餌を中に入れます。ただし、捕獲後の処置には専門的な知識が必要なため、できるだけ専門家に依頼しましょう。
侵入経路の特定・対策方法
イタチやハクビシンの侵入を防ぐには、屋根と壁の接合部、換気口、配管の周りなどをよく確認し、隙間があれば適切な材料で塞ぎます。また、樹木の枝が家に接している場合は剪定し、侵入経路を断つことも大切です。
イタチやハクビシン駆除時の注意点
イタチとハクビシンの駆除には、法律や安全面での注意点があります。適切な方法で対処することが重要です。
鳥獣保護管理法について
イタチとハクビシンは、鳥獣保護管理法で保護されている動物です。そのため、許可なく捕獲や駆除を行うことは違法です。駆除を行う場合は、必ず地域の自治体に相談し、適切な手続きを踏む必要があります。
駆除を行ってから報告に行くのではなく、きちんと事前に相談を行うか、直前でも良いので申請方法を確かめて問い合わせるようにしましょう。
許可申請の手続き
駆除の許可を得るには、自治体の担当窓口に申請書を提出します。申請完了後は許可証をもらって実際に捕獲を行い、その後借り受けた罠や許可証を返還していくなどの流れになります。
捕獲後の適切な処置
捕獲したイタチやハクビシンの処置方法は、事前に確認が必要です。自治体によっても処分の方針が変わってくるので、自分で処分しなくてはならないのか、あるいは他の方法が推奨されているのかは確認しましょう。
知識がゼロの場合は個人で処置を行うことは避け、必ず専門家に依頼しましょう。
予防対策と再発防止
イタチやハクビシンによる被害を防ぐには、予防対策が重要です。一度駆除した後も、再発を防ぐための対策を継続して行う必要があります。
餌場の除去
イタチやハクビシンを寄せ付けないためには、餌となるものを取り除くことが重要です。生ゴミはしっかりと密閉し、果樹の落果はすぐに拾い集めます。コンポストを使用している場合は、蓋付きのものを選び、害獣が中身を食べられないようにします。
侵入防止策
家の周りにフェンスを設置したり、樹木の枝を剪定したりすることで、イタチやハクビシンの侵入を防ぐことができます。また、屋根や壁の定期的な点検と修繕を行い、新たな侵入口ができないようにすることも大切です。
環境整備
庭や家の周りを清潔に保つことも、害獣対策として効果的です。草むらや積み木など、害獣が隠れやすい場所を減らし、見通しを良くすることで、イタチやハクビシンが寄り付きにくい環境を作ることができます。
Related Articles
関連コラム
-
ハクビシンの食べ物とは?被害対策から駆除まで徹底解説

- その他害獣
ハクビシンの生態と特徴 ハクビシンは鼻筋に白い線が特徴的な動物で、日本の多くの地域で見られます。家の...
-
屋根裏の不審な物音の正体は?動物侵入の特徴と対策、専門家による安全な駆除方法

- その他害獣
夜中や早朝、屋根裏から音が聞こえたら、何か動物がいるのかもしれません。本記事では、どんな動物が侵入し...
-
東京のハクビシン問題完全ガイド – 生態から対策まで徹底解説

- その他害獣
ハクビシンとは? 東京での生息状況 東京の街中で見かける機会が増えているハクビシン。この中型哺乳類は...
-
ハクビシンの駆除方法と費用相場は?効果的な対策と業者選びのコツ

- その他害獣
ハクビシンによる被害は、放置すればするほど深刻になりがちです。ハクビシンが家に住み着いている、あるい...









-300x169.jpg)
-300x169.jpg)