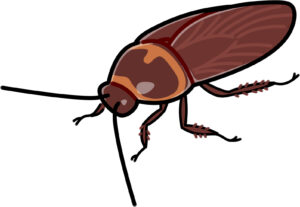東京のハクビシン問題完全ガイド – 生態から対策まで徹底解説

ハクビシンとは? 東京での生息状況
東京の街中で見かける機会が増えているハクビシン。この中型哺乳類は、近年都市部での目撃情報が増えていて注目され始めています。ハクビシンの生態を知り、東京でもハクビシンと遭遇する可能性やどんな被害が起こりうるのかなどを把握しておきましょう。
ハクビシンの特徴と生態
ハクビシンは体長約60センチ未満、尾が約30センチほどの大きさで、成獣の体重は3〜5キログラムほどです。その名前の由来にもなっている特徴的な白い顔の模様は、額から鼻にかけて伸びています。体色は灰色あるいは茶色を主とし、長い尾が特徴的です。
特筆すべきはその運動能力の高さです。木登りが非常に得意で、細い枝や電線の上も器用に歩きます。また、直径8センチメートルほどの小さな隙間さえあれば、そこから建物内に侵入できるほど体が柔軟です。
ハクビシンは雑食で、好物の果物や野菜だけでなく、小動物、昆虫まで食べられます。夜行性のため、日中は建物の屋根裏や木のうろ、森や林の中で過ごすことが多く、夜間に活動して食べ物を探します。
繁殖期は主に春から夏にかけてですが、年に2回出産することもあります。1回の出産で2〜4頭の子供を産み、生後約3ヶ月で離乳します。繁殖力の高さも、都市部での増加の要因と考えられています。
東京都内での分布状況
東京都環境局の調査によると、かつては主に多摩地域の山間部や郊外に生息していましたが、近年では都心部の公園や住宅地でも頻繁に目撃されるようになりました。
都市部の緑地や公園、住宅地の庭先など、人間の生活圏のすぐそばに生息しています。特に、古い木造建築物が多い地域や、緑が豊かな住宅地では目撃情報が多く寄せられています。
また、神社や寺といった歴史的建造物の周辺も、樹木が多く、建物にも隙間が多いため、ハクビシンの好む環境となっています。
生息数の推移
東京都内のハクビシンの正確な生息数は不明ですが、目撃情報や被害相談の件数は年々増加傾向にあります。
この増加傾向の背景として、まず、都市部の緑化政策により、ハクビシンの生息に適した環境が増えたことが挙げられます。また、冬季の気温が上昇し、越冬しやすくなったこと、天敵となる大型の肉食動物が都市部にはほとんど生息していないことも、要因とされています。
ハクビシンによる被害の実態
東京都内では、ハクビシンによるさまざまな被害が報告されています。その影響は農業から一般家庭まで幅広く、都内に住んでいるからといって被害を受けないとはもはや言えません。どんな被害が起こりうるのかを知り、必要に応じてすぐに対策できるようにしておきましょう。
農作物被害
東京でも、ハクビシンは果樹園や野菜畑に深刻な被害をもたらしています。被害が報告されている主な作物は、ブドウ、カキ、イチジク、トマト、ナス、キュウリなどがあります。これらの作物は糖度が高く、ハクビシンの好物です。
特に問題なのは、ハクビシンが収穫直前の最も価値の高い果実を食べてしまうことです。例えば、ブドウ農家では一晩で数十房もの高級品種が食べられてしまうこともあります。食べ残しの果実にカビが生えて商品価値が落ちるなど、二次的な被害も発生しています。
家屋侵入による被害
都内の住宅地では、ハクビシンが建物に侵入する事例が増えています。東京都環境局に寄せられる相談の中で、最も多いのがこの家屋侵入に関するものです。
ハクビシンは主に屋根裏や天井裏に住み着き、そこを寝床や子育ての場所として利用します。その結果、糞尿による悪臭や衛生問題をはじめ、断熱材や電気配線の破損、夜間の騒音被害などが起こってきます。
特に古い木造住宅や寺社仏閣では被害が深刻です。こうした建物は隙間が多く、ハクビシンが侵入しやすいので予防が難しいばかりか、被害が大きくなりがちです。
マンションでも安心できません。ベランダや屋上に侵入し、そこで糞尿をする被害も報告されています。
生活環境被害
生ゴミあさりによる衛生面の問題も指摘されています。ハクビシンは嗅覚が鋭く、生ゴミの臭いにすぐ気づきます。ゴミ置き場を荒らされることで、周辺が不衛生になったり、カラスなど他の動物も寄ってくるという二次被害も発生します。
公園や緑地では、ハクビシンによるゴミ箱荒らしや植栽の踏み荒らしなども報告されています。
ハクビシン対策の基本
ハクビシン対策を効果的に行うためには、対策の基本である「侵入させない」「餌を与えない」「環境を整える」の3つを守ります。これらを組み合わせて対策することで、より効果を見込めるでしょう。
侵入防止対策
建物の外周を細かくチェックし、8センチから10センチ四方の穴や亀裂がないか確認しましょう。まずは侵入の可能性がある箇所を見つけ出すことが重要です。
侵入防止対策として、以下のような方法が効果的です。
- 屋根や壁の破損箇所の補修
- 換気口や排水口への金網の設置
- 雨樋や縦樋の周りにネットや金網を巻く
- 屋根裏への進入口となる可能性がある隙間を塞ぐ
- 樹木の剪定(建物に接している枝を切る)
特に軒下や換気口、雨樋などは、ハクビシンが好んで利用する侵入経路となっています。例えば、軒下の隙間からハクビシンが侵入した事例では、隙間を金網で塞ぎ、さらにその上から板で覆うことで効果的に侵入を防止できました。
侵入防止対策を行う際は、ハクビシンが建物内に閉じ込められないよう注意が必要です。出入り口と思われる場所で小麦粉をまいて足跡を確認するなどして、ハクビシンがいないことを確認してから対策を施すことが推奨されています。
餌付け防止
ハクビシンをそもそも寄せ付けないためには、餌となるものを与えないことが重要です。ハクビシンは食べ物の匂いに誘引されやすいため、以下のような対策が効果的です。
- 生ゴミの管理:生ゴミは必ず密閉容器に入れ、夜間は外に出さないようにします。
- 果樹の管理:庭に果樹がある場合、実は早めに収穫します。落果した果実はすぐに片付け、放置しません。
- コンポストの管理:家庭菜園などでコンポスト(堆肥箱)を使用している場合、蓋付きのものを選び、周囲をネットで囲むなどの対策が必要です。
例えば、ゴミ置き場の改善によりハクビシンの出没が激減した事例があります。具体的には、従来の開放型のゴミ置き場を、扉付きの密閉型に変更し、さらに周囲に忌避剤を設置しました。この対策により、それまで頻繁に目撃されていたハクビシンの姿が見られなくなったそうです。
環境整備
ハクビシンの住処になりそうな場所を減らすことも、効果的な対策の一つです。以下のような対策が考えられます。
- 庭木の剪定:定期的に庭木を剪定し、枝が建物に接触しないようにします。
- 物置や倉庫の整理整頓:物置や倉庫内を整理し、ハクビシンが隠れられるような場所をなくします。/li>
- 庭の整備:庭に積まれた木材や資材、使っていない機材などは、ハクビシンの隠れ家になる可能性があるため整理します。
- 照明の工夫:ハクビシンは夜行性ですが、明るい場所は避ける傾向があるので、庭や建物の周囲にセンサー付きの照明を設置します。
- 樹木の剪定(建物に接している枝を切る)
東京都のハクビシン対策
東京都は2013年に「東京都アライグマ・ハクビシン防除実施計画」を策定しました。この計画は、特定外来生物であるアライグマと、外来種であるハクビシンの両方を対象としています。
具体的に実施した内容としては、都内全域でのハクビシンの生息状況の調査、捕獲事業、普及啓発活動、被害状況や対策効果に関するデータの収集・分析、区市町村や農業団体、研究機関などとの連携・対策などです。
この計画に基づき、都内各地でハクビシン対策が進められています。
Related Articles
関連コラム
-
ハクビシンの食べ物とは?被害対策から駆除まで徹底解説

- その他害獣
ハクビシンの生態と特徴 ハクビシンは鼻筋に白い線が特徴的な動物で、日本の多くの地域で見られます。家の...
-
屋根裏の不審な物音の正体は?動物侵入の特徴と対策、専門家による安全な駆除方法

- その他害獣
夜中や早朝、屋根裏から音が聞こえたら、何か動物がいるのかもしれません。本記事では、どんな動物が侵入し...
-
ハクビシンの駆除方法と費用相場は?効果的な対策と業者選びのコツ

- その他害獣
ハクビシンによる被害は、放置すればするほど深刻になりがちです。ハクビシンが家に住み着いている、あるい...
-
ハクビシンの足跡の特徴と見分け方!対策と駆除方法も

- その他害獣
家の周りで見慣れない足跡を見つけたら、それはハクビシンの足跡かもしれません。ハクビシンは近年、都市部...









-300x169.jpg)
-300x169.jpg)