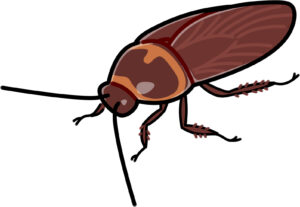ハクビシンの食べ物とは?被害対策から駆除まで徹底解説

ハクビシンの生態と特徴
ハクビシンは鼻筋に白い線が特徴的な動物で、日本の多くの地域で見られます。家の周辺や田畑、果てには都心にも見かけるようになっていて、発見頻度は高くなっていると言えます。ハクビシンを見かけたら、その周辺環境にハクビシンの好きな食べ物や巣があるのかもしれません。
ハクビシンの好きな食べ物や特徴を知り、被害を受けないようにあらかじめ対策できるようにしておきましょう。
ハクビシンの外見や生態の特徴
ハクビシンは体長40〜60センチメートル、尾長40〜50センチメートルほどの大きさで、体重は3〜5キログラムです。
額から鼻にかけて白い線があり、これが名前の由来となっています。体の色は灰色か茶色で、尾は黒っぽい色をしています。
日本では本州、四国、九州に広く分布しており、森林や山麓部、農村部、そして最近では都市部でも見られるようになりました。ハクビシンの適応力の高さから、様々な場所で生息するようになっているのです。都市部での目撃例が増えていることから、人間の生活圏との接点が増えていることがわかります。
ハクビシンの行動の特徴
ハクビシンは主に夜行性で、日中は木の洞や建物の屋根裏などで休んでいます。運動能力が高く、木登りが得意で、細い枝や電線も器用に渡ることができます。8センチメートル四方程度の小さな穴でも通り抜けられる柔軟な体を持っています。
高い運動能力と柔軟な体のおかげで、ハクビシンは様々な場所に入り込み、そして人の住居や田畑などで被害を起こしています。ハクビシン対策を考える際には、ハクビシンの身体的特徴と、それによってできることを把握しているのがまず重要です。
ハクビシンが好む食べ物
ハクビシンは多様な食べ物を好みます。どんな食べ物が好まれるのかを知っていれば、被害の拡大を防ぎ、ひいては予防する手がかりにもなります。
果物類
ハクビシンが最も好むのは甘い果物です。特にブドウ、柿、イチジク、ミカン、リンゴ、桃などを好んで食べます。果物は糖分が高く、ハクビシンにとって栄養価の高い食べ物となります。
ハクビシンは木登りが得意なため、高い位置にある果実でも簡単に食べることができます。そのため、果樹園や家庭の果樹に大きな被害が起こることがあります。
野菜類
果物の次に好むのが野菜類です。トウモロコシ、スイカ、カボチャ、イチゴ、ナスなどが畑で被害に遭いやすい野菜です。これらは水分や糖分が多く、特にトウモロコシは甘くて食べやすいので大好物として知られています。
畑では、完熟する直前のトウモロコシが狙われることが多く、農家にとっては大打撃です。イチゴやスイカなども甘くて水分豊富なので好まれます。畑で育つ野菜は、ハクビシンが簡単に食べられる場所にあるというのも被害が多い理由の一つです。
その他の好物
ハクビシンは雑食で、果物や野菜以外にも様々なものを食べます。例えば、小動物や昆虫、鳥の卵などを食べることもあります。また、人間の食べ残しや生ゴミも食べるため、都市部でも安心できません。都市部では、ゴミ置き場や飲食店の裏などで食べ物を探すハクビシンの姿が目撃されることがあります。
ペットフードや生ゴミの入ったゴミ袋を外に置いておくと、それもハクビシンの餌となる可能性があります。ハクビシンがいる可能性があるなら、徹底的に食べ物となりうるものを外に放置しないようにしましょう。
ハクビシンで起こりうる被害
ハクビシンが棲みつくと、被害は農作物にとどまらず、生活環境にも及ぶことがあります。どんな被害が起こりうるのかをまず知り、どの時点でどんな対策をすべきなのか把握しておきましょう。
農作物への被害
ハクビシンは果樹園や畑に侵入し、果物や野菜を食べたり傷つけたりします。特に、果物の食害は深刻です。
ハクビシンによる農作物被害は、一度に大量の作物を食べるのではなく、少しずつ多くの作物を傷つけるのが特徴で、それゆえに深刻です。ハクビシンは繰り返し同じ場所を訪れる傾向があるため、一度被害が出始めると、その後も継続的に被害が発生する可能性が高くなります。
農作物への被害が確認できたら、急いで対策を行うべきでしょう。
家屋への侵入と糞害
ハクビシンは建物の屋根裏や壁の中にすみつくことがあります。すみかになると、そこに集中して糞尿をしていくので悪臭や衛生問題を引き起こします。ハクビシンの糞は強烈で、臭いが室内にまで広がると被害が深刻です。すぐに臭いを取り除けるわけでもありません。糞には病原体が含まれている可能性があるため、健康上のリスクにもなります。
電線をかじったり、断熱材を巣作りに使ったりすることで、建物が損傷を受けることもあります。断熱材を巣材にされると、家の断熱性能が低下し、エネルギー効率が悪くなる可能性があります。
生活環境への影響
ハクビシンが住居内にすみついてしまったら、夜間の騒音や、ペットや乳幼児への怪我や病気の危害、感染症のリスクが起こり得ます。ハクビシンは夜行性のため、夜中に屋根裏や壁の中を動き回り、睡眠が妨げられたり、不安感を感じたりする人もいます。
放置していて良くなる問題でもないため、気がついた際は速やかに原因を取り除けるように動くのが良いでしょう。
ハクビシンの食害対策
ハクビシンによる被害を防ぐには、食事になりうるものをなくす、侵入できないようにする、追い払うなどの方法があります。一つのみを行うのではなく、状況に合わせて適切にできることをやっていきましょう。
①餌場をなくす
ハクビシンを寄せ付けないためには、まず餌となるものを取り除きます。落果はすぐに拾って処分しましょう。生ゴミは密閉容器に入れ、外に放置しないようにします。
②侵入経路を塞ぐ
ハクビシンの侵入を防ぐには、物理的に建物や畑の周りを守り固めます。
屋根裏や壁の中にすみつかれると、駆除が難しくなります。直径8センチほどの隙間がないか確認し、隙間や破損箇所は補強しましょう。
畑や果樹園の保護には、ネットや電気柵が効果的です。ネットは目の細かいものを選び、地面までしっかりと固定します。電気柵は、ハクビシンの習性を考慮して適切な高さに設置することが重要です。
③忌避剤の使用
ハクビシンは特定の匂いを嫌うため、専用の忌避剤を使用すると効果的です。市販の忌避剤のほか、唐辛子やわさびなどの辛味成分、ニンニクやネギなどの強い香り、柑橘系の精油なども効果があるとされています。
ただし、匂いは時間が経つにつれて効果が落ちるため、定期的な使用が必要です。化学的な忌避剤を使用する場合は、周辺環境への影響や人体への安全性を十分に確認してから使用するようにしましょう。
ハクビシンの駆除方法
ハクビシンの被害が深刻な場合、駆除が必要になることがあります。駆除を具体的に考える場合は、法律や安全面での注意点をおさえておきましょう。
ハクビシンの無許可な駆除は禁止
ハクビシンは「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」で保護されています。そのため、個人が勝手に捕獲や駆除をすることは禁止されています。
駆除が必要な場合は、まず市町村役場の担当窓口に相談し、許可を得てから捕獲を行うか、許可を持つ業者に依頼する必要があります。さらに捕獲後は、地域のルールに従って適切に処分しなければなりません。
処分方法としては放獣や殺処分などが含まれますが、具体的な方法は地域によって異なります。また、罠の設置場所や方法によっては、近隣住民に不安を与えたり、ペットが誤って捕獲されたりする可能性があります。周辺住民への配慮も必要です。
ハクビシンを捕獲した際の取り扱いにも注意が必要です。ハクビシンは攻撃的になることがあり、素人だと怪我をする可能性があります。
捕獲罠の種類と使用方法
自治体からの許可を得ることができれば、罠を設置することもできます。罠の種類としては、主に箱罠、かご罠、くくり罠が使用されます。
箱罠は金属製の箱型の罠で、ハクビシンが中に入ると扉が閉まる仕組みになっています。かご罠は箱罠と似ていますが、箱罠より軽量で運びやすいです。
くくり罠はワイヤーでハクビシンの足を捕らえる罠ですが、使用には特別な許可が必要です。罠の設置するのは、ハクビシンの通り道や被害のあった場所の近くが効果的です。餌にはハクビシンの好物である果物や野菜などを使います。定期的に罠を確認し、捕獲されたハクビシンを長時間放置しないことも重要です。
Related Articles
関連コラム
-
屋根裏の不審な物音の正体は?動物侵入の特徴と対策、専門家による安全な駆除方法

- その他害獣
夜中や早朝、屋根裏から音が聞こえたら、何か動物がいるのかもしれません。本記事では、どんな動物が侵入し...
-
東京のハクビシン問題完全ガイド – 生態から対策まで徹底解説

- その他害獣
ハクビシンとは? 東京での生息状況 東京の街中で見かける機会が増えているハクビシン。この中型哺乳類は...
-
ハクビシンの駆除方法と費用相場は?効果的な対策と業者選びのコツ

- その他害獣
ハクビシンによる被害は、放置すればするほど深刻になりがちです。ハクビシンが家に住み着いている、あるい...
-
ハクビシンの足跡の特徴と見分け方!対策と駆除方法も

- その他害獣
家の周りで見慣れない足跡を見つけたら、それはハクビシンの足跡かもしれません。ハクビシンは近年、都市部...









-300x169.jpg)
-300x169.jpg)