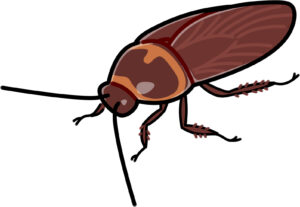屋根裏の不審な物音の正体は?動物侵入の特徴と対策、専門家による安全な駆除方法

夜中や早朝、屋根裏から音が聞こえたら、何か動物がいるのかもしれません。本記事では、どんな動物が侵入している可能性があるのか、またどんな危険性があるのかなど、詳しく解説します。また、再度侵入するのを防止するための方法も覚えておくと安心です。
屋根裏から不審な音や気配がするのはなぜ?
屋根裏から聞こえる音の正体
家屋から聞こえる音には、建物自体が発する音と、動物が引き起こす音があります。建物の音は、温度変化による木材の収縮や膨張、風による振動などが主な原因です。一方、動物が引き起こす音は、歩く音、引っ掻く音、鳴き声などがあります。動物の音は不規則で、特定の場所から繰り返し聞こえるのが特徴です。
季節や時間帯によっても音の原因は変わってきます。冬は動物が暖かい場所を求めて屋根裏に侵入しやすくなります。また、多くの動物は夜行性のため、夜中や早朝に活発に動き回る傾向があります。
建物の経年劣化による音や、雨漏りなどの影響で聞こえる音もあります。例えば、屋根材の劣化による雨漏りは、雨の日にポタポタと一定の箇所で水音がします。こうした音が聞こえたら、まず修理を検討すると良いでしょう。
屋根裏に侵入する可能性のある動物と特徴
屋根裏に侵入する可能性のある動物は主に5種類考えられます。ネズミ、ハクビシン、アライグマ、鳥類(主にハト)、コウモリです。それぞれ特徴的な行動パターンや痕跡があるので、特徴をおさえて侵入者を特定しましょう。
ネズミ
屋根裏に侵入する動物の中で最も一般的なのがネズミです。主にクマネズミとドブネズミが家屋に侵入します。
以下のような特徴をしていたら、ネズミだと考えてよいでしょう。
- 体長:10〜25cm程度(尾を含む)
- 行動:夜行性で、カリカリと物をかじる音や走り回る音を立てる
- 痕跡:5〜8mmほどの紡錘形の糞、かじり跡、足跡、体毛
- 侵入経路:1cm程度の小さな隙間からも侵入可能
ネズミは繁殖力が高く、一度侵入すると短期間で数が増える可能性があります。電線をかじる習性があるため、火災のリスクも高まります。
ハクビシン
ハクビシンは中型哺乳類で、近年は東京などの都市部でも見かけるようになりました。戸建ての屋根裏に侵入することも、また道路で発見されることもあります。
以下の特徴に当てはまれば、ハクビシンの可能性があります。
- 体長:50〜70cm(尾を含む)
- 行動:夜行性で、ドタドタと歩く音やゴソゴソと物を動かす音を立てる
- 痕跡:犬のものに似た糞(果実の種が混じることが多い)、足跡、体毛
- 侵入経路:木登りが得意で、屋根や壁を伝って侵入
ハクビシンは果物を好み、家庭菜園や果樹園に被害を与えることがあります。また、決まった場所で排泄する習性があるため、糞尿被害が集中しがちです。
アライグマ
アライグマもハクビシンと同様に、近年日本での生息域を拡大している外来種です。攻撃的な側面があるので、無闇に近づかないよう気をつけなくてはなりません。
アライグマの特徴には以下のようなものがあります。
- 体長:40〜60cm(尾を含む)
- 行動:主に夜行性だが、昼間に活動することもある。ドタドタと歩く音をたてる
- 痕跡:犬のものに似た糞(種子や動物の骨が混じることがある)、足跡(手のひらのような形)
- 侵入経路:木登りが得意で、手先が器用。屋根や壁をよじ登って侵入
アライグマは好奇心が強く、家の中の様々なものを荒らす可能性があります。
鳥類(主にハト)
鳥類の中でも、特にハトが屋根裏に侵入することが多いです。
特徴:
- 体長:30〜35cm程度
- 行動:主に昼行性。羽ばたく音や特有のクークーという鳴き声で判別できる
- 痕跡:白っぽい糞、羽毛、巣材
- 侵入経路:屋根の隙間や換気口から侵入
ハトは繁殖のために屋根裏を選ぶことが多く、一度巣を作ると執着します。糞による被害や、寄生虫の問題が発生する可能性があります。
コウモリ
屋根裏に侵入するコウモリは主に小型の種類です。
特徴:
- 体長:5〜10cm程度(翼を除く)/li>
- 行動:夜行性。高い超音波を発する
- 痕跡:米粒状の小さな糞、特有の臭い
- 侵入経路:1~2cm程度の小さな隙間からも侵入可能
コウモリは群れで生活する傾向があり、一度侵入すると多数が棲みつく可能性があります。糞尿による被害や、寄生虫の問題が懸念されます。
動物が屋根裏に棲みつく理由と潜在的な被害
動物たちが屋根裏を選ぶのはなぜでしょうか。動物は一度棲みついてしまうと、そのまま人間の生活に影響を与え続ける可能性があります。ここでは、動物が屋根裏を好む理由と、それによって起こりうる問題について説明します。
動物が屋根裏を好む理由
屋根裏は動物にとって理想的なすみかです。まず、外敵から身を守れる安全な場所です。また、家屋の暖かさが伝わるため、特に寒い季節には快適な環境となります。人間の生活圏に近いため、食べ物を見つけやすいという利点もあります。これらの要素がいくつも合わさっているため、動物たちは屋根裏を絶好の住処として選ぶのです。
建物へ起こる被害と影響
動物が屋根裏に棲みつくと、建物や人に様々な被害をもたらす可能性があります。
例えば、ネズミ類は近辺の電線をかじって断線や火災の危険を引き起こしたり、断熱材を巣作りに使って家の断熱性能を低下させたりします。
大型の動物だと体重で天井を傷めることがあります。大きさを問わず、糞尿による腐食や悪臭も深刻な問題となりかねません。これらの被害を放置すると、修理に高額な費用がかかる可能性があります。
住む人への被害と影響
動物が侵入すると、そこに住む人の健康にも影響があります。動物の糞尿は様々な病原体を含んでいる可能性があり、それらが乾燥して空気中に舞い上がることで、喘息の悪化など呼吸器系の問題を引き起こすおそれがあります。
動物が運んでくる寄生虫や害虫も問題です。夜間の活動的な時間、動物が動き暴れることで睡眠が妨げられ、慢性的なストレスの原因になることもあります。健康と快適な生活を守るためにも、早めの対処が重要です。
屋根裏の侵入者を特定する方法
屋根裏に何かが侵入しているかもしれないと感じたら、まずは侵入者を特定しましょう。ただし、安全が第一です。ここでは、侵入者を特定するための具体的な方法と、その際の注意点について詳しく説明します。
音や鳴き声による判別のコツ
動物の種類によって、出す音や鳴き声に特徴があります。以下に、各動物の特徴的な音をまとめました。
- ネズミ:カリカリと物をかじる音、小さな足音、キューキューという鳴き声
- ハクビシン・アライグマ:ドタドタと歩く音、ゴソゴソと物を動かす音
- 鳥類(ハト):羽ばたく音、クークーという鳴き声
- コウモリ:かすかな羽ばたき音(声は人間には聞こえにくい超音波を使用)
これらの音の特徴や、聞こえる時間帯を記録し、侵入者の手がかりとしましょう。夜中に聞こえる音なら夜行性の動物(ネズミ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ)の可能性が高く、昼間の音なら鳥類の可能性が考えられます。
痕跡(糞や足跡)の見分け方
動物は必ず痕跡を残します。以下は、各動物の特徴的な痕跡をまとめたものです。
- ネズミ:5~8mmの紡錘形の糞、小さな足跡、かじり跡
- ハクビシン:犬のものに似た大きめの糞(果実の種が混じる)、5本指の足跡
- アライグマ:犬のものに似た大きめの糞(種子や骨が混じる)、手のひらのような足跡
- 鳥類(ハト):白っぽい糞、羽毛、巣材
- コウモリ:米粒状の小さな糞、特有の臭い
これらの痕跡を注意深く観察することで、侵入者の特定に近づけます。ただし、糞や体液には病原体が含まれている可能性があるため、直接触れないよう注意しましょう。
安全な調査方法と専門家への相談時期
屋根裏の調査は危険を伴う可能性があります。まずはハシゴを使って外部から屋根や軒下を観察し、動物が入れそうな場所がないか確認します。もし侵入口を見つけ、そこから内部の調査をするならマスク、手袋、長袖・長ズボンなどを着用し、懐中電灯を持参しましょう。一人で危ない目に遭ってしまわないよう、必ず誰かと一緒に調査を行います。
探索は痕跡を見つけるのが目的です。もし生きた動物に遭遇した場合は、刺激しないよう静かに退去します。
侵入経路や動物の種類がわからない時、また痕跡が大量にありすぎる時、損傷が激しい時などは、自分だけでの対処が難しい可能性が高いので早めに専門家に相談するのがおすすめです。早期に対応すると、被害の拡大を防ぎ解決までの時間と費用を節約することにつながります。
動物の種類別駆除方法と注意点
屋根裏に侵入した動物の対処法は、その動物の種類や状況によって異なります。ここでは、種類別の駆除方法と追い出し方法、そしてそれぞれの注意点について説明します。ただしいくつかの野生動物は、捕獲や駆除の前に許可申請が必要なときがあります。
小型動物(ネズミなど)への対処法
ネズミ類に対しては、捕獲器や忌避剤が効果的です。捕獲器には、粘着式や生け捕り式があります。忌避剤には、超音波タイプや匂いを利用したものがあります。これらの方法を組み合わせることで、効果を高めることができます。
中型動物(ハクビシン、アライグマなど)への対策
ハクビシンやアライグマなどの中型動物は、法律で保護されています。自分で勝手に捕獲してはいけないので、追い出しと再侵入防止が主な対策です。追い出すには、強い光や音、匂いを利用した忌避剤が効果的です。また、屋外の餌源(生ゴミや果実など)を除去し、侵入口を塞ぐことで、再び戻ってこないようにすることが重要です。
専門家に依頼するべきケース
自力での駆除や追い出しには限界があります。特に、動物が子育て中の場合や、大量に棲みついている場合は、凶暴だったり手に負えないことがあるので、専門家の助けが必要になります。
不適切な方法で駆除すると、動物を傷つけたり、逆に家の中深くに追い込んでしまったりする可能性があります。さらに、動物の死骸や糞尿の処理は衛生上のリスクがあります。自力での対処に不安がある場合は、迷わず専門家に相談しましょう。
屋根裏への動物侵入を防ぐための方法
動物が一度屋根裏に侵入してしまうと、対処に時間と労力がかかります。そのため、事前に侵入を防ぐ対策を講じるのが非常に重要です。ここでは、効果的な予防策について説明します。
侵入される可能性のある場所を特定するポイント
動物の侵入を防ぐ最も効果的な方法は、侵入経路を特定し、それを封鎖することです。家の外周をよく観察し、小さな穴や隙間がないか確認しましょう。特に、屋根と壁の接合部、換気口、配管の周りなどに注意が必要です。
見つけた穴や隙間は、金網や補修材で塞ぎます。ただし、動物が中にいないことを確認してから封鎖しなくては意味がありません。
動物を家に引き寄せないためのポイント
動物を引き寄せる要因を取り除くことも重要な予防策です。生ゴミは蓋付きの容器に入れ、こまめに処理しましょう。果樹がある場合は、熟れた果実を放置しないようにします。また、庭木の枝が屋根に接している場合は剪定し、動物が屋根に登りにくくします。
餌となるものを減らし、アクセスを困難にすることで、動物が屋根裏に侵入するリスクを大幅に減らすことができます。
効果的な予防策と継続的なメンテナンス
予防策を講じた後も、侵入される可能性のある場所があるなら注意しておいた方が安全です。季節の変わり目や強風・大雨の後には、特に注意して家の外周をチェックしましょう。
屋根や外壁の劣化も動物の侵入を招く原因となるため、適切なタイミングで修繕することが大切です。継続的な取り組みによって、長期的に動物の侵入を防ぐことができます。
Related Articles
関連コラム
-
ハクビシンの食べ物とは?被害対策から駆除まで徹底解説

- その他害獣
ハクビシンの生態と特徴 ハクビシンは鼻筋に白い線が特徴的な動物で、日本の多くの地域で見られます。家の...
-
東京のハクビシン問題完全ガイド – 生態から対策まで徹底解説

- その他害獣
ハクビシンとは? 東京での生息状況 東京の街中で見かける機会が増えているハクビシン。この中型哺乳類は...
-
ハクビシンの駆除方法と費用相場は?効果的な対策と業者選びのコツ

- その他害獣
ハクビシンによる被害は、放置すればするほど深刻になりがちです。ハクビシンが家に住み着いている、あるい...
-
ハクビシンの足跡の特徴と見分け方!対策と駆除方法も

- その他害獣
家の周りで見慣れない足跡を見つけたら、それはハクビシンの足跡かもしれません。ハクビシンは近年、都市部...









-300x169.jpg)
-300x169.jpg)