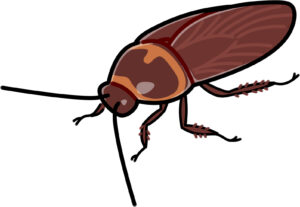【シロアリ被害】新築住宅を守るポイントをタイミング別に紹介!
-1024x576.jpg)
「シロアリ被害」と聞くと、中古住宅や築年数が経っている住宅をイメージする人が多いでしょう。
しかし、新築住宅でも油断はできません。
この記事では、大切な住宅を守るために、住宅が建つ前から居住後に至るまで、タイミング別の予防策やチェックポイントを紹介します。
【新築前】の予防策とチェックポイント
家を建てる時は、安心して長く暮らせるように設計段階からシロアリ対策を念頭に入れましょう。
夢のマイホームは、デザインや広さにこだわりがちですが、機能的な部分も十分に検討すべきです。
点検しやすい床下にする
床下は点検がしやすい造りにすることが重要です。
シロアリ被害に遭った時、床下は侵入経路になりやすい場所のひとつです。
そのため、定期的に点検や清掃ができるスペースを確保している方がいいでしょう。
設置する床下点検口は、人が出入りがしやすいサイズや場所を選ぶのがおすすめです。
さらに、開閉がしやすい場所に設置すると、点検や清掃のハードルが低くなります。
業者のみでなく自分でも点検ができると、床下の変化に気づきやすく、被害に遭ったとしても早期に対処が可能です。
床下の造りは主に以下の2つがあります。
布基礎
布基礎とは、壁や柱の下に「布状」にコンクリートが設置されている基礎形式のことです。
床からの立ち上がり部分にのみ、鉄筋が用いられています。
ベタ基礎に比べるとコストを抑えられますが、床部分のコンクリートが薄いため、湿気が上がりやすい造りです。
ベタ基礎
ベタ基礎とは、床下全体に建物の形に沿った鉄筋が組まれ、コンクリートが設置されている基礎形式のことです。
布基礎に比べるとコンクリートが厚く、使用量が多いため、コストを要しますが湿気がこもりにくくなります。
それぞれにメリット、デメリットがありますが、シロアリ対策にはベタ基礎が適しています。
床下はベタ基礎にして、移動しやすいようにシンプルな造りにしておくことがおすすめです。
布基礎とベタ基礎は、住宅が完成してからでは見分けが難しいため、注文住宅の場合は設計時に要望を伝え、建売住宅の場合は構造をきちんと確認しておく必要があります。
基礎断熱工法は避ける
基礎断熱工法は、基礎の中にシロアリが侵入してくるリスクがあるため、避けましょう。
基礎断熱工法とは、建物の基礎部分に断熱材を設置する方法で、室内と同じく床下空間を断熱できるメリットがあります。
しかし、断熱材はシロアリに狙われやすく、柔らかい素材なので侵食もされやすいです。
基礎と断熱材の隙間に蟻道を作りながら侵入してくるため、外見からは発見しにくくなります。
建物の断熱については、先ほど紹介したベタ基礎にすることで、効果が得られます。
床下を厚いコンクリートで覆うため、冷気が上がってくるのを防ぐことが可能です。
侵入経路になる隙間をなくす
シロアリは、わずかな隙間から侵入してきます。
侵入経路になりそうな隙間には、事前に対策をしておきましょう。
侵入されやすい場所は、以下の通りです。
- 基礎の立ち上がり部分
- 玄関ポーチ
- 配管周り
ベタ基礎はシロアリが侵入しにくい構造と述べましたが、立ち上がり部分のわずかな隙間をシロアリに狙われる場合があります。
コンクリートの継ぎ目部分であるため、隙間ができてしまうのは仕方ありません。
隙間ができてしまった場合は、シロアリを防ぐ薬剤を注入すると良いでしょう。
玄関ポーチは、玄関ドアとのすき間が土で繋がっていることが多いため、シロアリの侵入経路になりやすいです。
このすき間をコンクリートで埋めると、シロアリの侵入を防げます。
配管と基礎のすき間は、湿気がたまりやすく、シロアリが侵入しやすいです。
このすき間には、防蟻シートやパテで埋める対策をおすすめします。
湿気がこもらないように、換気口の設置場所にも気を配ると良いでしょう。
シロアリ予防措置を確認する
通常、住宅を建てる際には、ハウスメーカーにてシロアリ被害を予防する施工がされます。
これは、シロアリ被害を防ぐ「防蟻措置」を必要に応じて講じなくてはならないと、建築基準法で定められているからです。
防蟻措置はメーカーによってさまざまなので、どういった効果がいつまで続くのかを確認しておきましょう。
防蟻措置の工法は主に、バリア工法とベイト工法の2種類が採用されます。
工法別の特徴は以下の通りです。
バリア工法
- 壁に薬剤を散布したり、柱に薬剤を注入したりする
- 即効性がある
- シロアリ被害に遭った場合も短時間で広範囲に駆除が可能
- 薬剤によっては人体に健康上の影響がある
ベイト工法
- ベイト剤(毒エサ)を筒状のケースに含ませ、一定間隔で設置する
- シロアリがベイトを巣に持ち帰ると巣ごと撲滅が可能
- 即効性はない
- 安全性が高い
薬剤によって、効果が続く時間が異なります。
効果が得られる年数を確認することで、その後のメンテナンスの計画が立てられます。
しかし、薬剤は施工した時点から分解が始まるため、徐々に効果は薄れていきます。
目安の年数が経過するまで、同じ効果が続くわけではないと理解しておきましょう。
シロアリが好む木材を避ける
住宅に使われる木材は、シロアリが好む種類を避けましょう。
木造建築はもちろん、鉄筋コンクリート建築にも木材は使われます。
事前にハウスメーカーに使用する木材を指定したり、使用する予定の木材を確認したりすることをおすすめします。
シロアリが好む木材と好まない木材は、以下の通りです。
| シロアリが好む木材 | シロアリが好まない木材 |
|---|---|
| エゾマツ スプルース モミ セン ホワイトウッドなど |
ヒバ ローズウッド ヒノキ ケヤキ スギなど |
シロアリは、柔らかい木材を好む傾向にあります。
シロアリが好まない木材には、「ヒノキチオール」というシロアリが嫌う成分を含んでいるものが多いです。
しかし、好まないと言っても、必ず侵食されないとは言い切れないため、他のシロアリ予防策は必要でしょう。
住宅保証の内容を確認しておく
ハウスメーカーによって、シロアリ被害に関する住宅保証の内容は異なるため、確認しておく必要があります。
事前に保証内容を確認しておくと、万が一被害に遭ったとしても、落ち着いて行動できます。
冷静に速やかに行動すれば、被害の拡大を防ぐことが可能です。
なお、保証期間の確認も大切になります。
保証期間内に被害に遭った際、点検や処置の費用は保証会社にて無償で対応可能な場合が多いです。
シロアリ被害に遭うと、住宅に大きな損傷が発生する場合や高額な修復費用がかかる場合があります。
自己負担を軽減するために、保証内容と期間はあらかじめきちんと確認しておきましょう。
ただし、処置内容によっては追加費用が発生することもあるため、必要に応じて補償範囲の見直しをおすすめします。
いずれにしても、新築時に防蟻措置を講じていることが条件となるため、その作業がきちんと完了しているかを確認してください。
【入居後】の予防策とチェックポイント
新築前に予防策を講じたのみでは、長く住み続けるのに安心はできません。
居住し始めてからも被害に遭わないようにポイントを押さえながら、引き続き対策をしましょう。
シロアリが侵入してこない環境を整える
シロアリ予防の対策をしても、必ずしもシロアリが侵入しないとは限りません。
シロアリが好む環境づくりを避けることで、シロアリ被害の予防につながります。
シロアリが好む環境とは、以下の通りです。
- 湿気が多い
- 暗い
- カビが発生している
- ゴミが放置されている
湿気が多くて暗い場所である床下は、シロアリの侵入経路になりやすいです。
さらに、湿気が多いとカビが発生しやすい環境でもあります。
特に、水周りの床下や配管周りは注意が必要です。
環境を整えるには、床下換気扇や乾燥剤を用いて換気や除湿を心がけましょう。
そうすることで、カビの発生も防止できます。
また、家の外にダンボールや木材のゴミを放置していると、シロアリが寄りつく可能性があります。
セルロースを含むダンボールや木材は、シロアリの好物です。
家の周りにシロアリが棲みつくと、床下やコンクリートのすき間から住宅に侵入してくる危険性が高いため、家の外に対しても整理整頓を意識しましょう。
住宅の様子をチェックする
住宅の様子を定期的にチェックしていると、住宅の変化に気づきやすいでしょう。
もし、経年劣化によって住宅に亀裂ができていた場合、すぐに修復してシロアリの経路を塞げます。
また、すでにシロアリが棲みついていた場合でも、早期発見で被害を最小限に抑えられます。
シロアリが棲みついているかどうかは、住宅の様子から判明することが多いです。
普段のシロアリは、地中にいるように、暗い場所を好みます。
住宅に棲みついていたとしても、人の目に触れる場所に出てくることはほとんどありません。
シロアリは住宅の木材を侵食するため、木材の変化には注意しましょう。
シロアリに侵食された木材は、内部が空洞化するため、以下の症状が見られます。
- 床がきしむ
- 窓や扉が開けづらい
- 柱や壁を叩くと、空洞音がする
これらの症状が確認された場合は、シロアリ被害の可能性があるため、専門業者に相談しましょう。
ハウスメーカーの保証期間内であれば、住宅保証で対応することも可能です。
また、シロアリが侵入しやすい場所である床下は、定期的にチェックすると良いでしょう。
床下を点検して「蟻道」と呼ばれるシロアリの通り道を見つけた場合は、シロアリが侵入していると考えられます。
蟻道は、泥とシロアリの出す分泌液で作られたトンネルのようなものです。
暗い場所を好むシロアリは、蟻道を通って住宅に侵入します。
床下のチェックは、水周りや配管周りで発生した水漏れにも気づきやすいでしょう。
水漏れが発生するとカビが発生し、カビや腐食した木材を求めてシロアリが侵入してくるため、注意が必要です。
【新築5年目】の予防策とチェックポイント
新築から5年が経過すると、外観の変化はあまり感じられませんが、シロアリの被害に遭いやすくなります。
新築の際にシロアリ被害の予防策を講じたとしても、効果が薄れてくる時期です。
効果が薄れてシロアリ被害に遭わないためにも、このタイミングで行うべき予防策とチェックポイントを確認していきましょう。
シロアリ予防措置を再施工する
築5年が経過すると、新築時に使用した薬剤の効果が切れるため、防蟻措置を再施工しましょう。
自身での施工も不可能ではありませんが、特殊な薬剤や装備、ノウハウが必要となるため、専門業者への依頼をおすすめします。
住宅保証が継続可能かチェックする
ハウスメーカーの住宅保証が、新築5年目以降も有効であるか確認する必要があります。
通常、ハウスメーカーの住宅保証は「住宅を適切に管理している状態」で有効です。
この状態であると判断されるには、シロアリに関する点検や予防対策が適切にされているかも重要なポイントになるため、防蟻措置を施工することが必要です。
住宅の定期点検に加えて防蟻措置を施工し、住宅に安心して長く居住しましょう。
まとめ
大切な住宅がシロアリ被害に遭わないためには、あらゆるタイミングで予防策を講じる必要があります。
ハウスメーカーや専門業者の技術に頼ることで予防できる部分はありますが、最も大切なのは自身での点検やメンテナンスです。
シロアリの特徴や被害に遭いやすい環境を理解した上で、シロアリが侵入しない環境づくりを常に心がけることが重要になります。
また、シロアリの被害に遭ったとしても、早期発見が完全駆除への近道です。
発見した場合は、被害が広がる前に住宅保証制度を用いるか専門業者へ相談しましょう。
Related Articles
関連コラム
-
梅雨時期は要注意!シロアリ被害を防ぐためのポイントを紹介
-300x169.jpg)
- シロアリ
梅雨の時期は、シロアリ被害に遭いやすいといわれています。 この記事では、梅雨時期にシロアリ被害が多い...
-
【床下のシロアリ】侵入の兆候と自分でできる予防策を紹介!

- シロアリ
床下は、シロアリが侵入しやすい場所と言われています。 常に目に触れる場所ではないため、知らぬ間にシロ...
-
ベイト剤でシロアリ対策は万全?仕組みから効果的な使い方まで徹底解説!

- シロアリ
シロアリは、住宅に深刻な被害を与える厄介な害虫です。見えない場所で活動するため、気付いたときには被害...
-
シロアリに家をやられたら家は壊れるのか?被害の実態と防止策を徹底解説

- シロアリ
家に深刻なダメージを与えるシロアリ被害は、放置すれば家屋の構造そのものを脅かしかねません。「シロアリ...









-300x169.jpg)